「部下が本音を話してくれない」「相談される前にトラブルが起きてしまう」――そんな悩みを抱える上司は少なくありません。
実は、優れたマネジメントを行うリーダーほど、共通して高い「聴く力(傾聴力)」を持っています。
部下が心を開くかどうかは、上司の「話す力」ではなく「聴く姿勢」にかかっています。
この記事では、信頼される上司に共通する“聴く力”の特徴と、部下との関係を深めるための具体的なポイントを解説します。
なぜ「聴く力」が部下との信頼関係を左右するのか
多くの上司が「自分はちゃんと話を聞いている」と思っています。
しかし、部下の側から見ると「話を聞いてもらえていない」「理解されていない」と感じているケースが非常に多いのが現実です。
その差を生むのが、「ただ聞く」と「傾聴する」の違いです。
傾聴とは、相手の言葉だけでなく、その背後にある感情や意図にも耳を傾ける姿勢のこと。
この姿勢があるかどうかで、部下の心の開き方は大きく変わります。
信頼される上司は、「聴くこと」をコミュニケーションの中心に据え、部下が安心して話せる場をつくっています。
部下が心を開く上司に共通する「聴く力」の特徴
1. 相手の話を遮らず、最後まで聞く
話の途中で「つまりこういうことだよね」とまとめたり、アドバイスを急いでしまう上司は多く見られます。
しかし、部下にとってそれは「ちゃんと聞いてもらえていない」というサインになってしまいます。
信頼される上司は、部下が話し終えるまでしっかりと耳を傾け、話の内容だけでなく感情や背景も受け止めようとします。
この「遮らない姿勢」が、安心感と信頼の土台になるのです。
2. 評価や結論を急がず、まずは受け止める
部下が何かを話し始めたとき、すぐに「それはダメだ」「つまりこうすればいい」と結論を出してしまうと、本音は引き出せません。
傾聴上手な上司は、まず「そう感じたんだね」「それは大変だったね」と受け止めの言葉を返します。
評価を保留し、気持ちを受け止めるだけで、部下は安心して本音を話せるようになります。
3. 言葉にされていないサインを丁寧に拾う
信頼される上司は、部下の言葉だけでなく、表情・声のトーン・沈黙など非言語的な情報にも敏感です。
「言葉にできない違和感」や「言い淀み」に気づき、さりげなく「そこ、ちょっと気になったけど何かある?」と声をかけられる。
この一言が、部下にとっては「ちゃんと見てくれている」という大きな安心感につながります。
4. 自分の意見を押しつけず、相手の考えを引き出す
「こうあるべき」という上司の価値観を押しつけてしまうと、部下は萎縮して本音を話さなくなります。
聴く力のある上司は、自分の意見を一方的に伝えるのではなく、「あなたはどう思う?」「なぜそう考えたの?」と問いかけ、相手の考えを引き出します。
この対話姿勢が、部下の自立と信頼の両方を育てます。
5. 忙しい中でも“聴く時間”を確保している
どんなにスキルが高くても、そもそも「話を聞く時間」がなければ信頼関係は築けません。
信頼される上司は、忙しいスケジュールの中でも、短時間でもきちんと「聴く」時間を確保しています。
部下が「自分の話を大事に扱ってくれている」と感じることが、信頼の最大の基盤です。
「聴く力」がある上司がチームにもたらす好循環
傾聴を実践できる上司がいるチームでは、以下のような好循環が生まれます。
- 部下が安心して意見や悩みを話せるようになる
- 問題が早期に共有され、トラブルを未然に防げる
- 部下の主体性やモチベーションが高まる
- チーム全体の心理的安全性が向上し、生産性も上がる
一方で、上司が聞く姿勢を持たないチームでは、問題が表に出にくく、信頼関係が希薄になりやすい傾向があります。
まとめ|「聴く力」は、最強のマネジメントスキル
- 部下が心を開くかどうかは、上司の「話す力」ではなく「聴く力」にかかっている
- 遮らない・受け止める・非言語にも耳を傾けることが信頼構築のカギ
- 聴く姿勢がチームに安心感と心理的安全性を生み、成果にもつながる
「聴く」という一見シンプルな行為こそ、部下との信頼関係を築くための最強のマネジメントスキルです。
肩書きや立場ではなく、耳を傾ける姿勢こそが、人を動かす力になります。

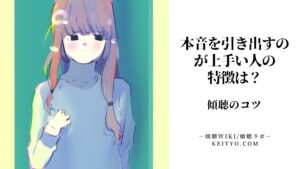

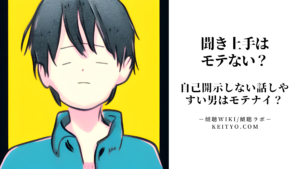

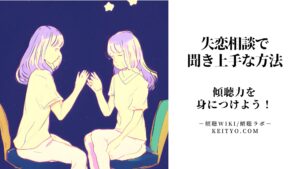
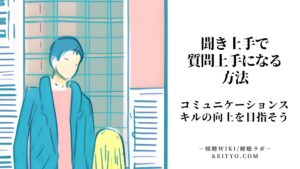
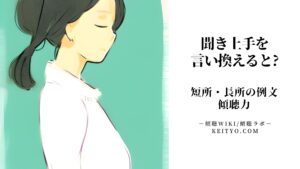
コメント